バレンタインデーにチョコを渡すのは日本だけ?最新のバレンタイントレンド5選
バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む


「お盆」とは、日本の伝統的な行事であり、ご先祖様の霊を迎え入れて供養する期間を指します。
毎年夏になると、全国各地でお墓参りをしたり、仏壇に供物を捧げたりする光景を目にすることがあるでしょう。
多くの日本人にとって当たり前の習慣となっているお盆ですが、そのルーツや意味を詳しく知っている方は少ないかもしれません。
お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、古代インドの仏教経典に由来する行事です。
母親が亡くなり、地獄で苦しむ姿を見た目連尊者(もくれんそんじゃ)が、釈迦の教えに従い多くの僧侶に供養を捧げることで救済されたという故事に基づいています。
この教えが中国を経て日本に伝わり、現在のお盆の形となりました。
本来は旧暦の7月15日を中心に行われていましたが、明治時代に新暦(太陽暦)に移行したことで、現在の日本では地域によって時期が異なるという現象が生まれました。
その違いが、のちに解説する「旧盆」「新盆」「月遅れ盆」などの形として表れています。
お盆の期間中は、迎え火や送り火、精霊棚(しょうりょうだな)などの伝統行事が行われます。
こうした風習には、それぞれ意味が込められており、ご先祖様の霊を丁寧に迎えて、無事にあの世へ送り返すという信仰が根底にあります。

「お盆はいつですか?」という問いに対して、全国共通の答えは実はありません。
地域によってお盆の時期が異なることは、意外と知られていない事実です。
この違いは、明治時代の暦の変更や地域文化の継承方法など、複数の要因が絡み合って生まれたものです。
お盆の時期は、大きく分けて以下の3タイプに分類されます。
東京都心部をはじめ、一部の地域では7月13日~16日ごろにお盆を行います。
これが「新盆(しんぼん)」あるいは「新暦盆」と呼ばれるものです。
旧暦の7月15日をそのまま新暦に置き換えたため、旧盆より1か月早い7月の実施となっています。
とくに東京23区内の寺院では、今でもこの日程でお盆の行事を行うのが一般的です。
沖縄県や奄美地方など、旧暦を重んじる地域では、旧暦の7月15日を基準にお盆を行います。
このため、毎年の暦に合わせて日付がずれ、8月中旬~9月初旬にずれ込むこともあります。
旧暦盆では、旧暦7月13日から始まり、15日に供養の中心となる行事を行い、16日に送り火を焚くという流れが一般的です。
全国的にもっとも多いのが「月遅れ盆」と呼ばれる形式で、8月13日~16日を中心に行われます。
これは旧暦の7月15日から1か月遅れた新暦の8月15日を基準にしており、現在の日本ではもっとも広く普及しているお盆の形です。
農繁期が終わるタイミングと重なったことや、会社の夏休み(お盆休み)との調整がしやすかったことも普及の一因となりました。
このように、お盆の時期には「正解」が1つではなく、地域性や文化的背景によってバリエーションがあるのです。
次の章では、実際に地域別にどのような時期にお盆が行われているのかを詳しく見ていきましょう。

お盆の時期は全国一律ではなく、都道府県や市区町村ごとに異なる場合もあるほど、多様な文化が息づいています。
以下では、地方ごとの傾向を解説しながら、主なお盆の時期を一覧で紹介していきます。
北海道は多くの地域で8月盆が主流です。
ただし、函館など一部の地域では旧暦盆が残っている場合もあります。
東北地方(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)ではほぼ全域が8月13日~16日にかけてお盆を行っています。
青森県の「ねぶた祭り」はお盆前の風物詩として有名です。
関東はやや複雑で、東京都心部(とくに23区内)は7月盆、それ以外の神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬は基本的に8月盆が主流です。
ただし、一部の寺院では7月に盆行事を行うなど、混在している地域も少なくありません。
新潟・長野・山梨・石川・富山・福井などの北陸・甲信越エリアでは、8月盆が定着しています。
静岡・愛知・岐阜の東海3県も基本は8月盆ですが、浜松市や名古屋市などの一部では旧盆の影響が残る地域もあります。
大阪・京都・兵庫など関西一円では8月盆が一般的です。
ただし、京都では7月末から盆行事が始まるケースも見られます。
中国地方(広島・岡山・山口・島根・鳥取)、四国(香川・愛媛・高知・徳島)においても8月盆が大勢を占めますが、旧盆や独自の伝統を守る集落も存在します。
九州の大部分は月遅れの8月盆ですが、長崎の精霊流しなど独自の文化が色濃く残っています。
沖縄県では旧暦に基づいてお盆を行うのが一般的で、毎年日付が異なります。
那覇や本島中南部では旧盆の3日間にあたるウンケー(迎え日)、ナカヌヒー(中日)、ウークイ(送り日)と呼ばれる特別な行事が行われます。
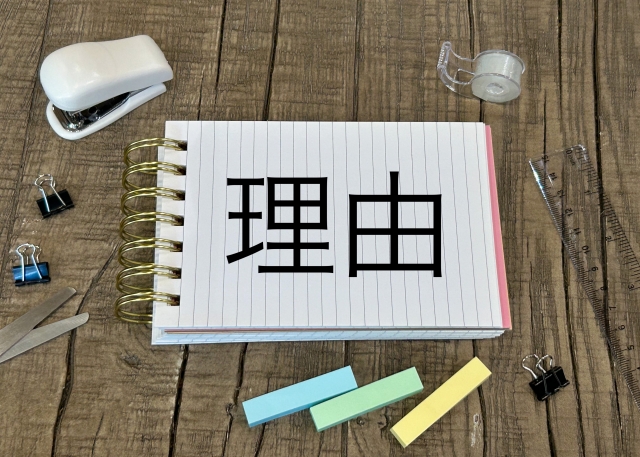
お盆の時期について話題にすると、「東京は7月でしょ?」という声が出てくることがあります。
これは決して間違いではありません。
実際、東京23区の多くの寺院では7月13日~16日にお盆の行事が行われるのが通例となっています。
しかし、同じ東京都でも多摩地域や周辺の市町村では、8月盆を行う家庭が大多数です。
この「東京のお盆=7月」という考え方が生まれた背景には、歴史的な経緯が関係しています。
明治政府が1873年に太陽暦(新暦)を導入した際、仏教寺院の多い東京では、新暦でそのまま7月15日をお盆とする動きが先行しました。
それにより、伝統的な旧暦7月15日ではなく、新暦7月15日が標準となり、「7月盆」が定着したのです。
一方で、地方では農作業の繁忙期と重なる7月のお盆は避けられ、1か月遅らせた8月盆(月遅れ盆)が広く採用されました。
また、8月には多くの企業が夏季休暇を設定していたことから、都市部でも8月盆が広まりやすい環境が整ったのです。
このように、東京とそれ以外の地域では「暦の解釈」と「生活習慣」の違いから、異なるお盆時期が生まれたといえます。
現在では、都内でも仕事や生活スタイルの多様化により、7月盆・8月盆が混在する家庭も多く、「どちらが正解」というよりも「家ごとの風習に従う」姿勢が一般的になっています。

お盆といえばお墓参りや仏壇へのお供えを思い浮かべる方が多いと思いますが、地域ごとに大きく異なる伝統行事や風習が根づいていることをご存じでしょうか。
全国には、単なる供養を超えて、お盆を「一大イベント」として盛り上げる文化が今なお息づいています。
長崎県では8月15日の夜に「精霊流し(しょうろうながし)」が行われます。
これは故人の霊を乗せた精霊船(しょうろうぶね)を引きながら町中を練り歩き、最後には海や川に流すという伝統的な行事です。
爆竹の音とともに精霊船が進む様子は壮観で、夏の風物詩として全国に知られています。
京都では8月16日の夜に「五山の送り火」が行われます。
大文字山をはじめとする5つの山に火を灯し、ご先祖様の霊をあの世へ送り出すという幻想的な行事です。
「大」の文字が浮かび上がる光景は、テレビ中継されるほど全国的にも有名です。
全国各地で行われている灯籠流しも、お盆を象徴する風習の一つです。
水に流した灯籠が、故人の魂を静かに送る様子を表現しており、川や海に幻想的な灯が浮かぶ光景は、観光客にも人気があります。
沖縄では旧暦のお盆(旧盆)に「エイサー」と呼ばれる踊りを披露します。
これは、青年団などのグループが太鼓と掛け声に合わせて集落を練り歩き、祖先の霊を慰めると同時に、地域の結束を示す行事でもあります。
三線の音色とリズムが、他の地域にはない沖縄独自のお盆文化を感じさせます。
多くの地域では、13日に「迎え火」を焚いてご先祖様を迎え、16日に「送り火」を焚いて見送ります。
しかしその方法もさまざまで、玄関先で焙烙(ほうろく)におがらを焚く地域、門前に提灯を灯す地域、道に松明を立てる地域など、多様な形があります。
このように、お盆は全国一律の儀式ではなく、それぞれの土地に根ざした信仰や習慣が融合した文化的イベントなのです。

お盆の時期は、全国的に帰省や旅行の移動が集中する繁忙期です。
とくに8月盆(13日~16日)に合わせて企業の夏季休暇が設定されているため、高速道路・新幹線・飛行機・宿泊施設すべてが混雑する傾向にあります。
スムーズに行動するためには、時期を見極めて事前準備を進めることが重要です。
毎年、お盆期間中には「Uターンラッシュ」「帰省ラッシュ」がニュースで報道されます。
たとえば2025年の場合、8月13日(水)が水曜日、8月16日(土)が土曜日にあたるため、12日(火)~14日(木)にかけての移動がピークとなる可能性が高いです。
帰省は前日の夜または午前中、Uターンは15日午後~16日午前が集中すると予想されます。
鉄道・航空・バスともに、この時期のチケットはすぐに売り切れるため、1か月以上前からの予約が理想です。
最近ではオンラインで座席指定・空席確認もできるため、直前のキャンセル待ちよりも、計画的にスケジューリングするほうが安心です。
混雑や高騰する旅費を避けたい方は、前後1週間程度ずらしたスケジュールで移動するのも一つの方法です。
多くの人が動く「お盆本番」を避けて帰省すれば、交通費・宿泊費を節約できる場合もあります。
地方によっては、お墓参りの時間帯、持参するもの、仏前に上がる際の服装マナーなどが細かく決まっていることがあります。
事前に家族や親戚に確認をとり、風習に合った対応を心がけるようにしましょう。
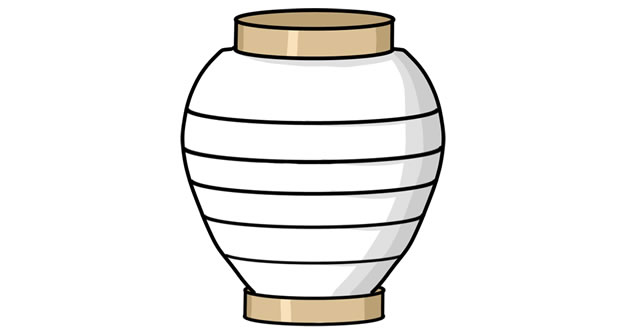
「新盆(にいぼん・しんぼん)」あるいは「初盆(はつぼん)」とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のことを指します。
通常のお盆とは異なり、より丁寧で正式な供養が行われるのが特徴です。
新盆では、白い提灯を飾ったり、僧侶を自宅に招いて読経してもらうことが多く、通常よりも厳粛かつ格式の高い儀式となります。
また、親戚や知人を招く場合もあり、規模が大きくなることもあります。
東京などの7月盆エリアでは、新盆も7月に行われますが、8月盆が主流の地域では当然ながら8月に実施されます。
さらに、旧盆を採用している地域では旧暦の7月15日前後に行われるため、毎年日付が変動するのが特徴です。
新盆の法要には多くの人が集まるため、供物の準備、会食の手配、香典返しなども必要になるケースがあります。
地域によっては香典を辞退する風習もあるため、しきたりや家族の意向をよく確認した上で準備することが大切です。

現在、日本で最も一般的なお盆の形式は「月遅れ盆」と呼ばれる8月13日~16日のお盆です。
なぜこのスタイルが主流となったのか、その背景を見ていきましょう。
本来の旧暦7月15日は、農作業の繁忙期と重なることが多く、供養どころではないという事情がありました。
そのため、1か月遅らせて8月中旬に行うほうが都合がよいという判断が、地方から徐々に全国へと広がっていったのです。
昭和以降、多くの企業が8月中旬に「お盆休み」を設けるようになり、社会的にも8月盆が前提のように扱われるようになりました。
現在では、学校の夏休みや会社の休暇がこの時期に集中することから、自然と人の流れが固定化しています。
近年では在宅ワークやフレックス制度の普及、ライフスタイルの変化により、「お盆=この日」という固定観念が少しずつ崩れ始めています。
今後は、各家庭ごとの都合に合わせた柔軟なお盆スタイルが広がる可能性もあるでしょう。

日本各地で行われてきたお盆行事ですが、都市化や核家族化の影響により、行事そのものが廃れつつある地域も増えてきています。
都心のマンション生活では、仏壇を置くスペースがなかったり、遠方の墓地に行けないといった事情で、お盆の儀式が簡略化されることがあります。
また、両親や祖父母が亡くなった後、実家の維持ができず「墓じまい」する家庭も珍しくありません。
精霊流しや盆踊りなど地域イベントも、少子高齢化により「担い手がいない」という理由で中止されるケースが増えています。
町内会や自治会の活動が縮小するなか、行事を継続するのが難しくなっているのです。
一方で、オンラインで墓参りができるサービスや、供養代行業者なども登場しています。
伝統とは違った形で、ご先祖様に感謝の気持ちを届ける方法が増えているのも現代の特徴です。

お盆は、日本各地で受け継がれてきた大切な風習です。
しかしその時期や方法は、一律ではなく、地域や家ごとの事情によって多様化しています。
7月盆・8月盆・旧暦盆など、形は違えど、根本にあるのは「ご先祖様に感謝し、敬う気持ち」です。
現代社会では、ライフスタイルの変化や都市化によって、お盆の形式が簡略化されたり、時には行われなくなってしまう家庭もあります。
それでも、自分のルーツや家族の歴史と向き合う機会として、お盆は貴重な節目であることに変わりはありません。
地方に残る伝統行事に触れることも、自分の育った土地の文化を知るうえで非常に意義深いことです。
精霊流し、灯籠流し、五山の送り火、エイサーなど、それぞれの土地に根ざした儀式には、長い年月を経て育まれた信仰とつながりの力があります。
また、お盆の時期を把握しておくことは、帰省や旅行、仕事のスケジュール調整にも直結する実用的な知識となります。
親戚づきあいのマナーを守るうえでも、「自分の地域ではどうなっているのか?」を知ることは重要です。
ご先祖様を迎え、送り出すという一連の流れは、ただの形式ではなく、心を整える時間でもあります。
忙しない日常のなかで、一度立ち止まり、大切な人たちを思い出すきっかけとして、これからもお盆の文化を見直すことが求められています。

A:いいえ。
地域によって異なります。
東京など一部では7月盆(7月13~16日)、全国の大多数は8月盆(8月13~16日)、沖縄などは旧暦で行う旧盆と、時期が分かれています。
A:東京都心部(特に23区)は7月盆が主流ですが、東京都下や周辺の市町村、また企業や学校のスケジュールによっては8月盆が一般的な家庭もあります。
家ごとの慣習に従って問題ありません。
A:沖縄は独自の文化圏を形成しており、旧暦による行事が多く残っています。
旧盆(旧暦の7月13~15日)を採用しており、エイサーやウークイなど特有の行事が行われます。
A:親戚や実家への手土産には、日持ちのする和菓子や地元の名産品が好まれます。
仏壇へ供える供物も兼ねる場合は、お線香や果物、焼き菓子などが無難です。
A:事前や事後に墓参りをする、仏壇に電話で手を合わせる、遠隔地からお供え物を送るなど、できる範囲で気持ちを表す方法があります。
大切なのは形式よりも「供養の心」です。

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

節分はいつ?実は年によって日付が違う? 節分の由来と意味を知ろう 節分の代表的な風習 地域によって違う?節分の習慣と風...続きを読む

仕事始めとは?意味と由来を知ろう 仕事始めはいつから?カレンダーによって変わるケースも 業種によって異なる仕事始めのタ...続きを読む

お年玉とは?その意味と由来 お年玉の相場はいくら?年齢別の目安 お年玉は何歳まであげるべき? 地域ごとの違いとマナー ...続きを読む

成人式とは?本来の意味と由来を知ろう 18歳で成人なのに、成人式は20歳? 成人式の服装|男性・女性それぞれの選び方 地域によって違う?成人式の開催日やスタイ...続きを読む

おせち料理とは? おせち料理の基本構成と意味 地域ごとに異なるおせち料理 最近の"進化系おせち"事情 おせち料理は手作...続きを読む

年賀状とは?その意味と由来を改めて知ろう 年賀状はいつまでに出す?基本マナーと注意点 年賀状のデザインにこだわるコツと...続きを読む

はじめに|年末大掃除のタイミングと意味 年末大掃除の順番と計画の立て方 場所別|年末大掃除のポイントと具体的なやり方 ...続きを読む

ふぐの旬はいつ?一般的な旬のイメージとその理由 実は年中楽しめる?ふぐの種類と季節ごとの味わい 産地によって旬は違う?...続きを読む

シングルマザーが働ける条件の良い求人はこちら シングルマザーの手当 いくらもらえる?所得制限は? ...続きを読む

目次 国民健康保険の減免の条件 国民健康保険を減免できる所得金額の目安 国民健康保険の減免の申...続きを読む

就学援助制度を受けられる年収の目安 就学援助制度などの手当は、ある程度の年収がある人なら対象外になります。経済的に余裕が...続きを読む

シングルマザーの手当の児童扶養手当のもらい方です...続きを読む