卒業旅行とは?いつから始まった?地域や学校による違いと最近のトレンドをわかりやすく解説
卒業旅行とは?どんな意味がある行事なのか 卒業旅行はいつから始まった?その歴史と背景 卒業旅行はいつ行く?時期の目安と...続きを読む


年の初めに、日頃お世話になっている方々や、久しく会っていない友人・知人に向けて新年の挨拶を届ける。
それが年賀状の本質です。
古くから日本では「年始回り」といって、親戚や恩師の家を訪れて新年のご挨拶をする風習がありました。
その風習が、明治時代の郵便制度の発展とともに簡略化され、年賀状という形での挨拶文化が定着していきました。
年賀状は単なる形式的な習慣ではなく、「あなたのことを思っています」「今年もよろしくお願いします」という心のやりとりです。
忙しい現代社会においては、つながりを保ち続ける一つの手段でもあります。
年賀状のルーツは、平安時代にさかのぼります。
当時の貴族たちは、年始に親しい人へ手紙を送って新年の挨拶をしていました。
その文化が江戸時代に町民層へと広がり、明治4年(1871年)に郵便制度が整備されると、年賀状の文化が一気に広まりました。
特に明治時代後半には、「年賀郵便」制度が開始され、「元日に年賀状が届く」という仕組みが整備されたことで、新年の風物詩として年賀状が日本中に浸透していきます。
また、昭和の高度経済成長期には、企業や個人を問わず、お付き合いの証として大量の年賀状が交わされる時代になりました。
ポストにぎっしりと年賀状が届く元旦の朝は、多くの人にとって楽しみのひとつだったことでしょう。
近年はSNSやメールの普及によって、年賀状を出す人が減っているのも事実です。
特に若い世代では、LINEやInstagramで「あけおめ」のメッセージを送るスタイルが主流になりつつあります。
しかしその一方で、「やっぱり紙の年賀状がうれしい」という声も根強くあります。
手書きのメッセージや写真入りのデザインには、画面越しには伝わらないぬくもりや誠実さがあるからです。
また、年賀状は相手の住所や状況を確認できるきっかけにもなります。
「最近引っ越したみたいだな」「あ、苗字が変わってる!」というように、人との距離を再認識するツールにもなり得ます。

年賀状の最大のマナーは、「元日に届くように送ること」です。
相手のポストに元旦に年賀状が届くことで、「新年のはじまりとともにご挨拶ができる」という日本特有の美意識が感じられます。
日本郵便では毎年「年賀状特別扱い」の期間を設けており、例年12月15日~25日の間に投函すれば、ほとんどの地域で元日に届くよう手配されます。
12月25日を過ぎると元日に届く可能性が下がるため、遅くともこの日までに投函を済ませておくのが理想です。
年賀状には「年賀」と朱書きされたはがきを使用することで、通常の郵便物とは別に年始の配達に回されます。
以下の表は、一般的な年賀状のスケジュールの目安です。
| 日付 | 対応内容 |
|---|---|
| 12月15日~25日 | 年賀状の投函推奨期間(元日到着を目指す) |
| 12月26日~31日 | 元日には届かない可能性あり(1月2日以降の配達) |
| 1月1日~7日 | 「年賀状」としての扱いは継続(松の内の間) |
| 1月8日以降 | 「年賀」ではなく通常はがき扱い、寒中見舞いを検討 |
ポストの集荷時間にも注意が必要です。
締切日の夜に出しても、翌日扱いになる場合がありますので、可能であれば数日前までに余裕を持って投函しましょう。
もし年賀状を出しそびれてしまった場合は、出す時期に応じて文面を調整するのが大人のマナーです。
寒中見舞いは、「寒さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか」という相手の体調を気遣う趣旨の挨拶状であり、年賀状に対する返信や喪中見舞いとしても使える便利なはがきです。
遅れてしまった理由を書く必要はありませんが、気になる場合は以下のように添えると良いでしょう。
「新年のご挨拶が遅くなってしまい、申し訳ありません。」
「本年も変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。」
取引先や仕事関係の相手に送る年賀状は、とくにマナーを意識する必要があります。
元日に届くようにするのはもちろんのこと、宛名や社名に間違いがないかも必ず確認しましょう。
近年は企業によっては「年賀状を廃止しました」とアナウンスしているケースもあるため、先方の方針を事前に把握しておくのが望ましいです。
また、ビジネス年賀状では「賀詞(がし)」の使い方にも注意が必要です。
例えば「賀正」「迎春」は本来、目上の人に使うには失礼にあたる略語とされるため、正式な「謹賀新年」「恭賀新年」などを使うのが無難です。

年賀状を作成する際、「手書きか、印刷か」は悩みどころです。
どちらが正解というわけではありませんが、それぞれに異なる良さがあります。
印刷された年賀状は、デザイン性が高く、統一感もあり、短時間で多くの人に送ることができるという点で便利です。
近年は自宅のプリンターやネット印刷を使えば、自分らしいデザインを気軽に作れるようになっています。
一方、手書きの年賀状には、温かみや誠意が感じられるという魅力があります。
すべてを手書きするのが難しい場合も、ひと言だけでも直筆メッセージを添えることで、「あなたのために書いた」という特別感が生まれます。
近年人気の「写真入り年賀状」は、家族や子どもの成長記録、ペットとの暮らしなど、自分たちの「今」を届ける手段として喜ばれています。
ただし、万人に好まれるとは限らないため、送る相手を選ぶ配慮も必要です。
特にビジネス関係や目上の方への年賀状に、プライベートな写真を載せるのは避けたほうが無難でしょう。
また、写真を載せる場合は以下のような点にも注意しましょう:
特に家族写真では、明るく前向きな印象を与える構図を意識することで、見た人の心を温かくすることができます。
年賀状には古くから使われてきた「おめでたい」モチーフがあります。
これらをデザインに取り入れることで、より年始らしい華やかさが演出できます。
たとえば、
色については、赤・金・白などが定番です。
これらは「祝い」の気持ちを表す色として、華やかさや希望を感じさせます。
一方で、寒色系を使う場合は、水引きや和柄などで和の雰囲気を演出すると、落ち着いた印象を与えることができます。
印刷された年賀状だけではやや味気なく感じられることもあります。
そこに手書きでひと言メッセージを添えると、より心のこもった一枚になります。
ポイントは以下の3つです:
手書きのひと言は長くなくても構いません。
送る相手の年齢や関係性によって、年賀状のデザインも少し工夫することで、より好印象を与えることができます。
| 送る相手 | おすすめデザインのポイント |
|---|---|
| 親戚・家族 | 写真入り・干支のモチーフ・温かみのある色合い。子どもの成長報告も◎。 |
| 友人 | カジュアルなデザイン。ユーモアやポップな干支イラストも人気。 |
| 会社関係・取引先 | 和風・フォーマルなデザイン。干支+「謹賀新年」などきちんとした表現を。 |
| 年配の方 | 落ち着いた色合い・筆文字風の賀詞・古典的な縁起物が好まれる。 |
自分らしさを活かしつつ、受け取る相手の気持ちに配慮したデザインを心がけると、より良い年賀状になります。
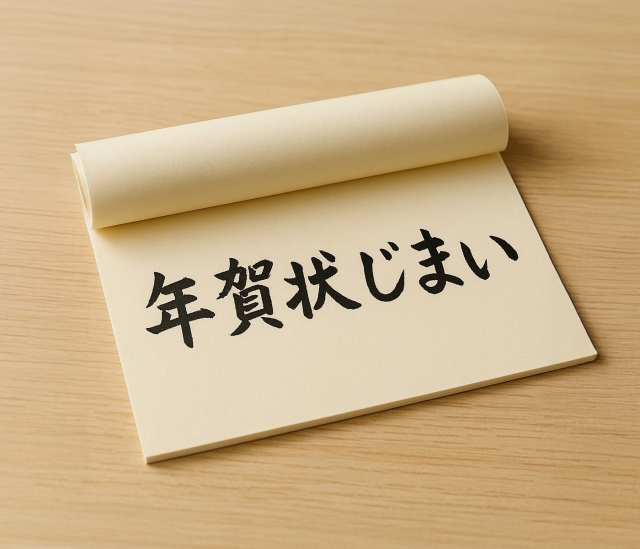
近年、「年賀状じまい」を選ぶ人が増えています。
かつては年賀状を数十枚単位で出すことが当たり前のように思われていましたが、今ではその習慣を見直し、年賀状のやりとりを終了するという決断をする人が、若い世代からシニア層まで広がってきています。
背景には、以下のような理由があります:
このように、年賀状じまいは個人の生活スタイルや価値観の変化を反映した、自然な流れとも言えます。
年賀状をやめることを検討していても、「長年続けてきたから」「急に出さないのは失礼ではないか」と迷う方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、以下の点をひとつの判断材料にしてみてください:
そして何より、「年賀状じまい=絶縁」ではありません。
これからのつながり方を見直すひとつのきっかけと考えることで、より柔軟に判断できるようになります。
年賀状じまいをする場合は、最後の年賀状にその旨を丁寧に記しておくと、相手も安心し、良好な関係を維持しやすくなります。
以下に例文をご紹介します。
誠に勝手ながら、年齢的な理由により、本年をもちまして年賀状でのご挨拶を控えさせていただきたく存じます。
長年のお付き合いに心より感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご厚誼をお願い申し上げます。
今後はSNSなどでのご挨拶に移行させていただきたく、本年をもって年賀状によるご挨拶を終了させていただきます。
どうぞ変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
私事で恐縮ですが、身辺整理を機に年賀状によるご挨拶を終了させていただくことといたしました。
長年のお心遣いに深く感謝申し上げます。
年賀状をやめても、相手との関係が続くことはもちろん可能です。
大切なのは、感謝の気持ちを伝え、関係を断ち切る意思ではないことをきちんと示すことです。
また、年賀状をやめる一方で、
といった工夫をすれば、人とのつながりを保ちつつ、無理のないコミュニケーションが可能になります。
中には「自分だけが一方的にやめて失礼では?」と心配される方もいますが、相手もまた同じように迷っていたり、受け入れてくれることが多いです。
大切なのは、その気持ちを丁寧に伝えることです。

スマートフォンの普及とともに、年賀状の代わりにLINEやメール、Instagram、X(旧Twitter)などのSNSで新年の挨拶を交わす人が増えています。
特に若い世代では、紙の年賀状を出した経験がないという人も少なくありません。
こうしたデジタルツールによる挨拶も、マナーさえ押さえておけば失礼にはあたりません。
ポイントは以下のとおりです。
たとえデジタルであっても、相手への感謝や気遣いが伝わるメッセージを意識することで、好印象を残すことができます。
年賀状文化の変化は、世代によって大きく異なります。
| 年代 | 年賀状に対する傾向 |
|---|---|
| 10代~20代 | 年賀状離れが顕著。LINEやSNSでの新年挨拶が主流。そもそも「年賀状を出したことがない」という声も多い。 |
| 30代~40代 | 子どもが生まれたタイミングで写真入り年賀状を出す傾向。同時にSNSでも挨拶を行うハイブリッド型が多い。 |
| 50代~60代 | 長年の習慣として継続中だが、年賀状じまいを意識し始める世代。健康や終活を理由に縮小傾向。 |
| 70代以上 | 手書き派が根強いが、高齢を理由に年賀状じまいを決意する方が増加。 |
このように、年賀状文化は確実に変化しており、今後は「紙の年賀状+デジタル挨拶」の使い分けがさらに広がっていくと考えられます。
「すべてをデジタルに切り替えるのは味気ない」
「でも紙の年賀状は手間がかかる」
そんなジレンマを抱える方におすすめなのが、紙とデジタルを組み合わせた"ハイブリッド型"の年賀状です。
たとえば、以下のような方法があります。
このように、工夫次第で紙もデジタルも活かせる時代です。
一人ひとりに合った"ちょうどよい距離感"での挨拶を考えることが、これからの年賀状スタイルかもしれません。

年賀状が毎年たまっていくと、「いつまで取っておけばいいのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
思い出として大切に保管したい気持ちと、収納スペースの問題。
その狭間で揺れる気持ちはごく自然です。
法的な保存義務があるわけではないため、個人間の年賀状は自分の気持ちで処分して問題ありません。
ただし、以下のような場合には注意が必要です。
感情的なつながりが強いものは、無理に捨てる必要はありません。
一方で、形式的な印刷のみの年賀状や数年以上交流がない相手のものなどは、一定期間を経て整理しても良いでしょう。
保管する年賀状は、箱にまとめて入れておくだけでなく、見返しやすく・管理しやすい方法にすることで、思い出としての価値が高まります。
おすすめの収納方法は以下のとおりです:
年賀状の写真をGoogleフォトやEvernoteなどに保存すれば、災害時の備えにもなり、整理もしやすくなります。
年賀状には、住所・氏名・家族構成などの個人情報が含まれているため、処分する際はそのまま捨てるのは避けましょう。
主な処理方法は以下の2つです。
クロスカット機能のあるシュレッダーなら、復元が難しく安全です。
シュレッダーがない場合は、住所・名前の部分をしっかりカットし、別のゴミと混ぜて出す工夫を。
なお、燃えるゴミとして出せるかどうかは自治体によって異なるため、各自治体のルールを事前に確認しておきましょう。
年賀状の処分や見直しにあたって、環境への負荷を減らすことも意識したいポイントです。
毎年数億枚が発行される年賀はがきは、実は相当な紙資源を消費しています。
こうした背景から、環境に配慮して「年賀状を出さない」「デジタルに切り替える」という人も増えてきました。
また、日本郵便や一部の自治体では、年賀はがきのリサイクルを行っている場合もあります。
こうした制度を利用することで、廃棄ではなく再資源化に貢献できます。
さらに最近では、以下のような取り組みも見られます:
年賀状という文化を守りながらも、時代の価値観に合わせて見直していく柔軟性が、これからの年賀状との向き合い方として求められているのかもしれません。

時代の流れとともに、年賀状の在り方は少しずつ変化しています。
以前のように「すべての知人・友人に出す」という文化から、「本当に大切な人へ、気持ちを込めて送る」スタイルへと移りつつあります。
そんな中で変わらないのは、年賀状が「つながりを確かめる手段」であるという本質です。
毎年決まって届く一枚のハガキに、相手の生活や気遣いが感じられたとき、私たちは思わず心が温まります。
年賀状には、人と人とのご縁を再確認し、未来への希望を語る力があります。
「年賀状を出すのが面倒」
「印刷ばかりで味気ない」
そんな声が聞こえることもあります。
でも、義務感で出すのではなく、自分のスタイルで感謝を伝えるのなら、それは十分に価値ある行動です。
たとえば:
どんな方法でも構いません。
大切なのは、「あなたのことを思っています」と伝える気持ちです。
年賀状をやめることも、続けることも、どちらも"相手を思う選択"であることに変わりはありません。
年賀状じまいを決めた方は、その節目に感謝の気持ちを伝えることで、これまでのご縁に丁寧に向き合えます。
一方で、年に一度の挨拶を大切に続けていく方もまた、長く温かい関係を育む大切な手段として年賀状を使っています。
形にとらわれず、"相手を思う気持ち"を軸にした年始のご挨拶を、これからも続けていけると良いですね。

日本郵便によると、例年12月25日までに投函すれば元日に届くとされています。
ただしポストの集荷時間や地域によって差があるため、できれば12月20日頃までに出すと安心です。
松の内(1月7日)までに届くようであれば通常の年賀状として問題ありません。
それ以降になる場合は「寒中見舞い」として挨拶状を送りましょう。
丁寧な言葉でその旨を伝えれば失礼にはなりません。
感謝の気持ちを込めた文面にすることで、円満に年賀状のやりとりを終了できます。
たとえば「年齢的な事情により、年賀状でのご挨拶を本年限りとさせていただきます」など、やめる理由と感謝の言葉を簡潔に伝えるのが基本です。
本文中にも具体例を掲載していますのでご参考ください。
印刷会社にもよりますが、12月中旬~下旬にかけては注文が集中するため、早めの手配がおすすめです。
12月10日頃までに注文すれば余裕をもって受け取れるケースが多いです。

卒業旅行とは?どんな意味がある行事なのか 卒業旅行はいつから始まった?その歴史と背景 卒業旅行はいつ行く?時期の目安と...続きを読む

卒業式はいつ行われる?基本的な時期と日程の目安 卒業式の日程が違う理由とは? 卒業式の服装マナー|学生・保護者・先生の...続きを読む

春一番とは?意味と定義をやさしく解説 春一番はいつ吹く?発表される時期と条件 春一番の由来と歴史 春一番の過去デー...続きを読む

針供養とは?その意味と目的 針供養はいつ行われる?日程と由来 針供養のやり方|実際の供養方法を解説 針供養を行っている...続きを読む

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

節分はいつ?実は年によって日付が違う? 節分の由来と意味を知ろう 節分の代表的な風習 地域によって違う?節分の習慣と風...続きを読む

仕事始めとは?意味と由来を知ろう 仕事始めはいつから?カレンダーによって変わるケースも 業種によって異なる仕事始めのタ...続きを読む

成人式とは?本来の意味と由来を知ろう 18歳で成人なのに、成人式は20歳? 成人式の服装|男性・女性それぞれの選び方 地域によって違う?成人式の開催日やスタイ...続きを読む

ふぐの旬はいつ?一般的な旬のイメージとその理由 実は年中楽しめる?ふぐの種類と季節ごとの味わい 産地によって旬は違う?...続きを読む

シングルマザーが働ける条件の良い求人はこちら シングルマザーの手当 いくらもらえる?所得制限は? ...続きを読む

目次 国民健康保険の減免の条件 国民健康保険を減免できる所得金額の目安 国民健康保険の減免の申...続きを読む

就学援助制度を受けられる年収の目安 就学援助制度などの手当は、ある程度の年収がある人なら対象外になります。経済的に余裕が...続きを読む

シングルマザーの手当の児童扶養手当のもらい方です...続きを読む

もう人間関係に疲れた…と感じたら|人間関係がしんどい時の心の守り方と距離の取り方...続きを読む